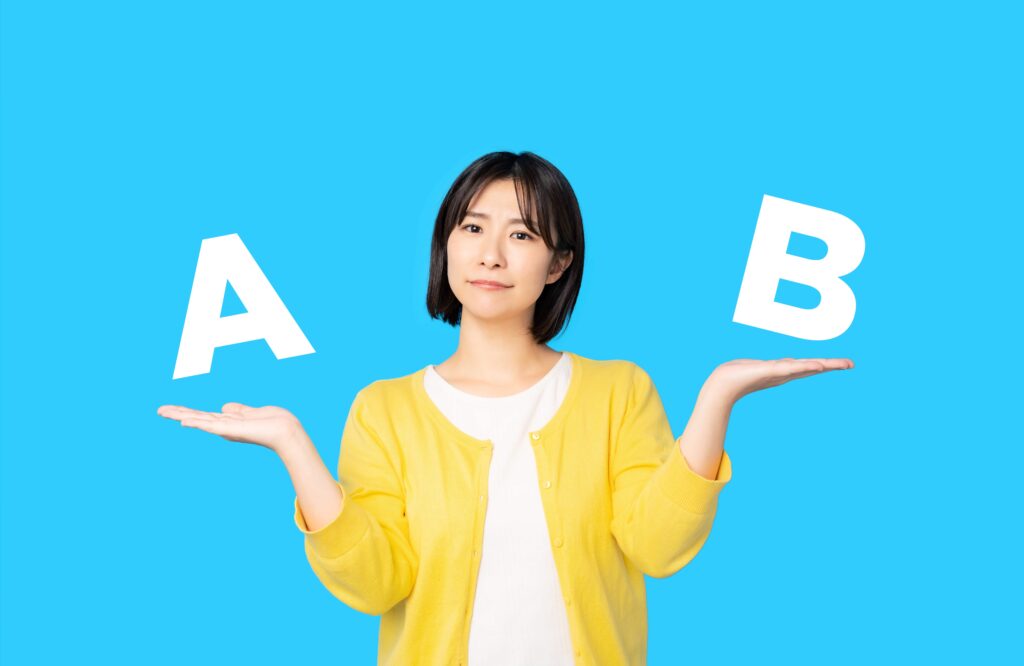手足の麻痺やしびれなど、脳梗塞の後遺症に悩まされている、という方も多いのではないでしょうか。脳梗塞の後遺症は、運動機能への影響や感覚のずれなど日常生活に支障をきたすものも少なくありません。本記事では、脳梗塞の後遺症から回復するための効果的なリハビリについてくわしく紹介します。
治療しても残りやすい脳梗塞の後遺症
脳梗塞は、治療後にも後遺症が残りやすい病気のひとつです。後遺症により日常生活に支障が出るケースも少なくありません。脳の損傷部分と程度によって、さまざまな症状が現れます。脳梗塞の後遺症は、早期治療と適切なリハビリにより改善が見込めます。脳梗塞とは
脳梗塞とは、脳の血管が詰まり血流が途絶えることで、酸素やエネルギーが十分に供給されずに脳細胞が壊死する脳卒中のなかでももっとも多い病気です。脳の血管が詰まる原因は、動脈硬化や不整脈、高血圧などさまざまです。また、脳梗塞によって壊死した脳細胞が元に戻ることはありません。そのため、脳が損傷した部位や範囲によって、手足のしびれ、麻痺、言葉が話せない、めまい、呂律が回らないなどの後遺症が残るケースもあります。脳梗塞の後遺症は、早期治療と適切なリハビリにより改善が見込めます。
運動麻痺
運動麻痺とは、脳が大きなダメージを受けたことで脳からの指令が伝わらなくなり、手足の動きが不自由もしくは完全に動かせなくなる状態です。脳梗塞の後遺症は、片側だけの麻痺が一般的です。運動麻痺には、筋肉の過度な緊張により硬直している痙性麻痺と筋肉が緩み力を入れづらい弛緩性麻痺の2種類があります。
感覚障害
感覚障害は、触覚や温度覚、痛覚などの感覚が鈍くなったり、過敏になって痛みを感じたり、さまざまな症状があります。発症後から半年程度経ってから、しびれが強くなるケースもあります。高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳の損傷により認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障がでる状態です。注意力や記憶力、感情のコントロールなど、外見からは分かりにくいため、見えない障害といわれています。言葉が出てこなかったり、集中力が続かなかったり、物忘れが激しいなど、人によって症状はさまざまです。後遺症を軽くするにはリハビリが重要!
後遺症が残りやすい脳梗塞ですが、症状を軽くするには早期にリハビリを開始することが重要です。さまざまな症状があるため、ひとりひとりに合ったリハビリが効果的でしょう。早期にリハビリを開始することが重要
後遺症を軽くするには、発症直後からのリハビリが推奨されています。早期のリハビリにより症状が軽くなったり、合併症を予防できたり、脳梗塞による死亡率を低下させるなど、さまざまな効果が期待できます。発症後、早期にリハビリを開始することで脳の神経組織が破壊される前に血流が再開されるため、脳機能が回復しやすくなる可能性があるでしょう。長期的な寝たきり状態を避けられるため、廃用症候群の防止にも役立ちます。
ひとりひとりの症状に合わせたリハビリが効果的
脳が損傷した部位や範囲などによって、必要なリハビリは異なります。現在では、自己負担で利用できる出張リハビリトレーニングを提供するサービスが増えつつあります。自宅にいながら国家資格を有するプロの質の高いリハビリを受けられると評判です。脳梗塞のリハビリと3つの段階について
脳梗塞を発症後には、急性期・回復期・生活期の3つの段階があります。急性期の段階からのリハビリ開始が効果的だといわれています。【発症~2週間】急性期のリハビリ
急性期のリハビリは、身体機能の低下を防止する目的で行います。発症から48時間以内にリハビリを開始できることが望ましいとされています。長期的な寝たきり状態は、内臓機能の低下、うつ病、認知症など、体力や認知機能に悪影響を及ぼしかねません。筋肉の萎縮や関節の動きが悪くなるなど、身体機能の低下にもつながりさまざまな不調を引き起こす原因になります。
定期的なストレッチや臨床訓練、ADL訓練など、日常に必要な動作を自分でできるように訓練するとよいでしょう。それぞれの症状に合わせた機能回復訓練など、適切なリハビリを重ねることで症状の回復が期待できます。