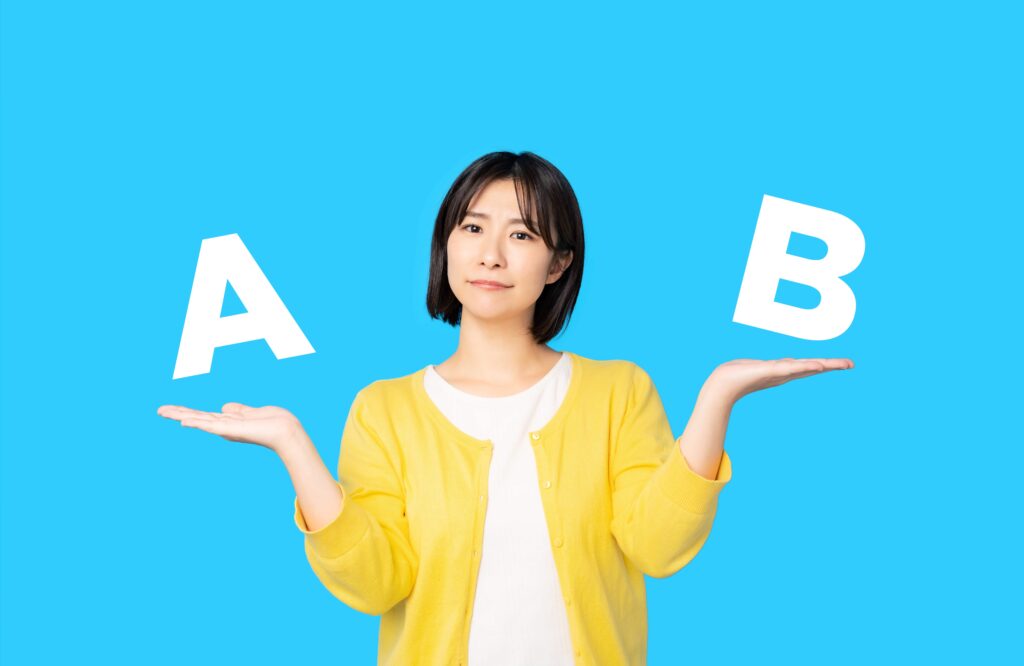介護予防とは、要介護状態にならないために予防策を講じ、健康を維持するために行うものです。介護の必要がなく、自立した日常生活を送れる期間である健康寿命を延ばすことが重要です。健康寿命を延ばすカギは、介護予防にあります。この記事では、介護予防の必要性や具体的な取り組みについて詳しく解説します。
なぜ必要?「介護予防」とは
まずはなぜ介護予防が必要なのか、詳しく解説していきます。介護予防とは
介護予防とは、要介護状態になることをできる限り遅らせ、要介護状態であってもその悪化をできる限り防ぎ、さらに軽減を目指すことです。要介護状態は、要支援1~2および、要介護1~5の要介護状態区分該当する高齢者のことを指します。要支援区分は、身体または身体障害により6か月にわたり継続して日常生活の一部に支障がある状態のことをいいます。要介護者は、要支援よりも深刻な状態であり、6か月に渡って日常生活の動作の一部またはすべてに介助が必要とする状態です。
要介護状態になると、身体も心も充実させることが難しくなるでしょう。そのため、介護予防を通じて要介護状態になることを防いだり維持したりすることを、国を上げて支援しています。
介護予防の現状と必要性
健康寿命と平均寿命はともに延び続けていますが、その間隔が縮まる傾向は見られません。さらに高齢者は増加しているため、65歳以上の要介護者は増加傾向にあります。現代では、介護難民や老々介護など、老後の暮らしに不安を抱える人の数は少なくありません。この現状を考慮すると、介護予防に必要性はますます高まることが予想されます。
介護予防のための取り組み
介護予防は、早い段階で廊下のサインをとらえて予防策に取り組み、健康や身体機能を維持するものです。今後、介護が必要な高齢者が増えていくことが予想されているため、各市町村や地域包括支援センターなどが主体となった介護予防事業への取り組みが増えています。以下では、具体的な介護予防のための取り組みについて詳しく紹介します。介護予防の機能強化
リハビリ専門職が介護予防の体制強化に取り組んでいます。リハビリ専門のスタッフが定期的にかかわることで、施設職員へのアドバイスを行いながら、通所サービスや訪問支援での自立をサポートします。通いの場の充実
地域住民の地域の交流の場として通いの場を展開しています。要介護の状態になっても通い続けられるように、介護の専門家が定期的に関与しています。介護予防の推進
高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進を行っています。地域ケア会議などで自立支援プログラムを共有し、個人のケアマネジメントを専門家がサポートします。介護予防のための基本チェックリスト
厚生労働省では、介護予防の必要がある65歳以上の高齢者の介護予防に役立てるために、基本チェックリストを作成しています。運動機能や口腔の状態、生活機能、栄養状態、認知症などの症状や機能を、25項目の設問でチェックできます。チェック後には、介護予防を実施するための教室やサービスに参加することが可能です。
毎日の取り組みで健康寿命を伸ばそう!
健康寿命は、介護の必要がなく自立した生活を送れる期間のことをいいます。単に長生きするだけはなく、元気に過ごす期間を延ばすことで、生活の質を高められます。毎日の小さな取り組みが、将来の自分を支える大きな力になるでしょう。運動する習慣をつける
運動は筋力を維持するだけでなく、心の健康にも効果的です。ストレッチやウォーキングなど、無理のない範囲内で継続できる運動を習慣にしましょう。運動が苦手な人でも、できることから始めてみることが大切です。食事で病気予防
バランスの取れた規則正しい食事は、病気の予防につながります。野菜を多く摂ることを心がけ、塩分や糖分の摂りすぎに注意することが大切です。また、噛むことで脳を活性化させられるので、安易に柔らかい食べ物や介護食を取り入れることは避けましょう。そして、定期的な水分補給も大切です。高齢になると、のどの渇きを感じにくくなってしまうので、家族や周囲の人と声を掛け合って水分補給を心がけましょう。
睡眠と心のケア
質の高い睡眠をとることは、体の修復や脳のリフレッシュに役立ちます。就寝前には、リラックスできる時間をもつことが大切です。趣味を楽しんだり人と交流したりすることで、心の健康を維持できるでしょう。周囲とのつながり
家庭や地域、職場など、さまざまなつながりの中で生きています。しかし、高齢者が要介護状態になると外出の機会が減ってしまうので、周囲とのつながりが減ってしまいます。周囲とのつながりが減ると、身体状態の悪化や認知症を引き起こす可能性が高まるでしょう。地域社会において幅広い世代とのつながりを持つことが、健康寿命を延ばすことにつながります。